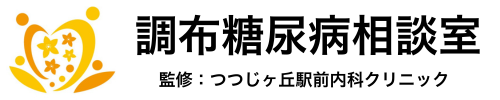糖尿病による全身への影響
糖尿病は、血糖値が高いだけというイメージですが、それだけでは終わらないのが糖尿病です。血糖が高い状態が続くということは、長期間に渡って全身の血管がボロボロになり、最終的には、全身の様々な臓器や組織に深刻なダメージを与えてしまう病気です。高血糖の状態が継続すると、血管の内側(内壁)にダメージがあり、最終的には、血管が詰まったり、もろくなりやすくなります。血管がボロボロになるという状態は、細い血管はもちろんのこと太い血管にも影響してしまい、全身の臓器で障害が発生します。
糖尿病の初期には、自覚症状が出ないことがほとんどであり、こわいところです。症状があれば、病院を受診しようとしますが、症状がないとなかなか受診は難しいですよね。しかし、症状が特にないまま、血管の障害が徐々に進行していきます。早期に気づくためにも、定期的な健康診断や、血糖管理をすることがとても重要となります。
糖尿病と寿命の関係
2型糖尿病と診断されると、糖尿病になっていない人と比べると、平均余命が6年短くなるという恐ろしいデータがあります。(Lancet Diabetes Endocrinol,. 2023 Oct;11(10):731-742. doi: 10.1016/S2213-8587(23)00223-1. Epub 2023 Sep 11.Life expectancy associated with different ages at diagnosis of type 2 diabetes in high-income countries: 23 million person-years of observation)
糖尿病は血糖を上げるだけではなく、全身の色々な合併症を発症することにより、重篤な病気を発症する年齢が早めると考えられています。腎不全、心筋梗塞、脳梗塞など、重篤な状態に陥る危険性が、糖尿病ではない人に比べて高くなります。
大血管障害(動脈硬化性疾患)
糖尿病は、動脈硬化を進めてしまい、太い血管に重篤な影響を及ぼします(大血管障害)。血糖が高い状態は、血管を固くし、血管の内側の壁に、コレステロールの塊などが付着し、血管が狭くなり血流が悪くなります。この動脈硬化などの変化によって、全身の血管で重大な疾患が発生します。
心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓の周りにある栄養や酸素を運ぶ血管(冠動脈)が閉塞や狭くなってしまうことで、心臓への血流が悪くなる病気です。軽症の場合は、狭心症と呼ぶような疾患になります。症状は、胸部の痛み、冷や汗、などが突然出てきます。しかし、糖尿病患者さんの場合、神経が鈍くなっている事があり、心筋梗塞が起きているのに症状を感じていない場合があります。そのため、軽度のときには気付けず、重症化してしまうことがあります。
脳梗塞
脳へ酸素や栄養を送っている血管が詰まり、脳への血流が途絶えるため、脳が酸素不足になる病気です。症状としては、意識障害、半身麻痺、言語障害などが起こります。後遺症が残ることも多く、重症の場合は、歩くことが困難になることもあります。
糖尿病の細小血管障害
糖尿病によって細い血管が傷ついてしまうと、「(しんけい)神経障害」「(め)網膜症」「(じん)腎症」の三つがあります。これらは「糖尿病の三大合併症」と言われており、発症しやすい順番順でもあり、それぞれの頭文字を取って「しめじ」という覚え方をします。
糖尿病による神経障害
糖尿病の合併症にて、一番早く出やすいのが神経障害です。高血糖であることが、細い血管を傷つけるため、神経に栄養を送れなくなり、神経がダメージを受けます。特に手足の先端から症状が出やすいです。
症状としては、冷感、足のしびれ、ピリピリとした痛みなどがあります。神経障害は、皮膚の感覚を鈍らせるため、ストーブなどによるやけどに気づかず、重症化してしまい、最終的には足の感染にまでいたってしまうこともあります。
神経には、自律神経というものもあり、自律神経は、体温調節や、血圧調節など様々な働きをしています。自立神経が障害されると、血圧が変動しやすくなり立ちくらみや、排尿障害、汗を異常にかく、勃起不全(ED)などの様々な症状が出現します。
神経は一度障害されてしまうと治すことは困難であるため、神経障害を起こさないように予防をすること、血糖値をコントロールをすることがとても大事です。
糖尿病網膜症
網膜は、視覚した情報を脳に伝える組織であり、この網膜が損傷すると、眼が見えにくくなります。糖尿病は関係がないと思われるかもしれませんが、実は目の奥にある網膜には、細い血管が張り巡らされています。そのため、血糖が高い状態が続くと血管が障害され、視力障害が起こります。
糖尿病網膜症は進行度によって、名前が変わります。
①(初期)単純網膜症
自覚症状がないことが多いですが、網膜にちいさな出血ができることがあります。
②(中期)増殖前網膜症
網膜に届く血流が障害され、網膜に酸素が届きにくくなります。
③(末期)増殖網膜症
出血や網膜剥離を起こし、視力が低下しやすくなります。
糖尿病性腎症
腎臓は、余分な水分や体の中の老廃物を尿として捨てている臓器です。また、腎臓は、血を作る作用や、血圧を調整する機能もあります。
そんな腎臓も血管が集まっている臓器であり、血糖が高い状態が継続すると、腎臓の血管が損傷を受け、排出機能が低下していきます。その結果、尿のタンパクを外に出さないようにする腎臓が壊れているため、尿の中にタンパクが出てきてしまい、蛋白尿が尿検査で検出できるようになります。
腎臓は最終的に壊れてしまうと、尿が出なくなってしまうため、人工透析という治療が必要になってしまいます。
末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)
高血糖によって、血管が損傷をうけるため、足の動脈が詰まりやすくなり、足の血流が悪化します。安静時に足の痛みがないけれども、歩行時には足が痛くなるという症状がでます(間欠性跛行)。悪化すると、足の血流が途絶えて、壊疽を起こし足を切断しなければならなくなります。
糖尿病と認知症
糖尿病の方は、認知症になりやすいということがわかっています。糖尿病患者さんはアルツハイマー型認知症に約1.5倍、血管性認知症に約2.5倍なりやすいという報告があります。
認知症を発症すると、糖尿病の治療や生活が難しくなる傾向があります。薬の飲み忘れをしやすい、食事管理がうまくできないなど、血糖値が悪化しやすくなります。このように、糖尿病と認知症は悪循環になりやすい関係にあります。