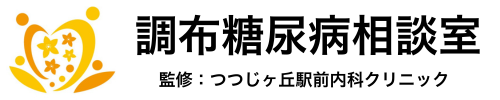糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が、継続的に高い状態が続く病気です。早期発見を行い早期から治療を開始することにより、深刻な合併症を予防することができます。
ここでは、糖尿病の診断基準や検査方法について、日本糖尿病学会のガイドラインを基に詳しく解説します。
糖尿病の診断基準
日本糖尿病学会が定める診断基準では、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)と血糖値を組み合わせて、診断を行います。
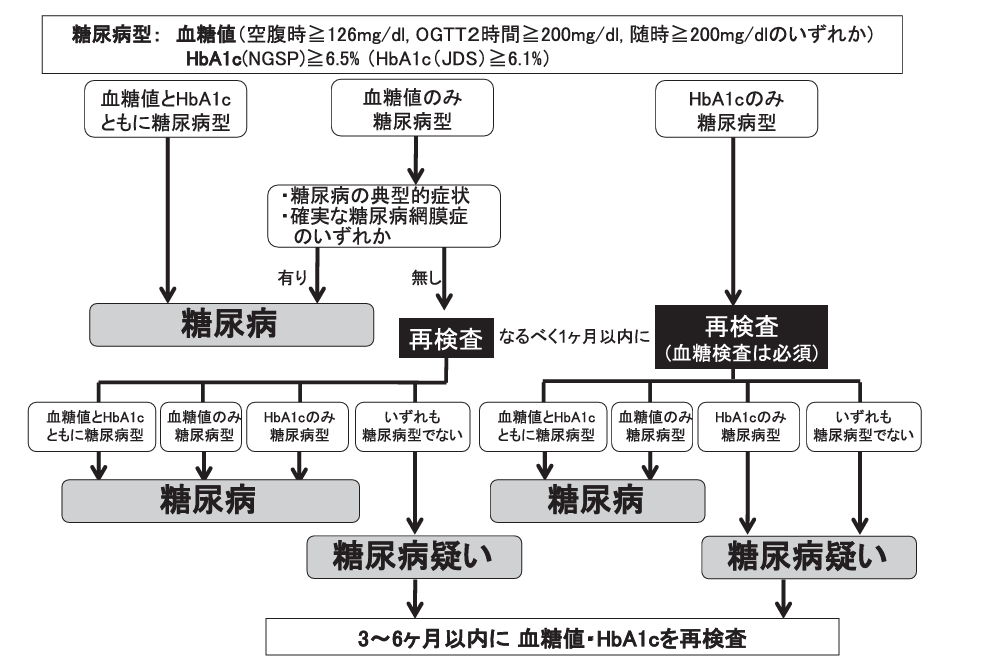
※ 糖尿病の典型的症状(口渇、多飲、多尿、体重減少など)
検査項目
①血糖値検査
血糖値は、食事によって影響を受けるため、いくつかの測定方法があります。
【空腹時血糖値】
空腹時血糖値は、インスリンを分泌する能力を評価します。
測定方法:10時間以上絶食した状態で測定(朝食前が多い)
基準値・・正常:70〜99mg/dL
正常高値:100〜109mg/dL
糖尿病型:126mg/dL以上
【随時血糖値】
食後の血糖上昇を把握します。
測定方法:食事時間とは関係なく測定
基準値:糖尿病型:200mg/dL以上
【75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)】
境界型糖尿病(糖尿病予備群)や糖尿病を早期に発見するための検査です。食後高血糖の有無を正確に評価できます。食後高血糖(血糖値スパイク)は動脈硬化による心血管疾患(脳梗塞や心筋梗塞)のリスクを高めます。
検査手順:10時間以上絶食状態で、空腹時に測定。75gのブドウ糖を摂取し、30分後、1時間後、2時間後の時点で測定
判定基準・・正常型:2時間値が140mg/dL未満
境界型:正常型と糖尿病型のいずれにも該当しない
糖尿病型:2時間値が200mg/dL以上
②HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)
HbA1cは、直近約2ヶ月間の血糖状態を示す値です。赤血球中のヘモグロビン(Hb)にブドウ糖がくっついているもので、赤血球の寿命(約120日)とともに変動します。
空腹時血糖値のみの検査では、食後高血糖を評価できないため、HbA1cも検査することにより糖尿病の診断が可能です。
基準値・・正常:4.0〜5.5%
正常高値:5.6〜5.9%
糖尿病予備群:6.0〜6.4%
糖尿病型:6.5%以上
特徴は、食事の影響を受けず、採血のタイミングが関係ないことです。
③その他の血糖指標
【グリコアルブミン(GA)】
過去1〜2週間の血糖の変動を示します。
基準値・・正常:12〜16.5%、 糖尿病:16.5%以上
【1,5-AG(1,5アンヒドログルシトール)】
過去数日間の血糖の変動を示します。血糖値が180mg/dL以上で尿糖が出る始めると、1,5-AGは低下します。
基準値・・正常:15〜45μg/mL、糖尿病:15μg/mL以下
④尿検査
尿中の糖の有無を検査し、糖尿病の状態を把握します。しかし、糖尿病の初期では、尿糖が陰性のこともあります。
糖尿病治療中の定期検査
糖尿病腎症
血液検査:血清クレアチニン、eGFR(推算糸球体濾過量)、血清タンパク・血清アルブミン
尿検査:尿蛋白、尿潜血、尿中アルブミン
糖尿病網膜症
眼底検査
視力検査
眼圧測定
糖尿病神経障害
神経伝導速度検査
足の触覚・振動覚検査
心血管疾患
心電図検査
心臓超音波検査(心エコー)
運動負荷試験
ABI検査(足関節上腕血圧比)
頸動脈超音波検査
その他の検査
腹部超音波検査(脂肪肝、肝硬変、肝がんの評価)
便潜血検査(大腸がんのスクリーニング)
CT検査